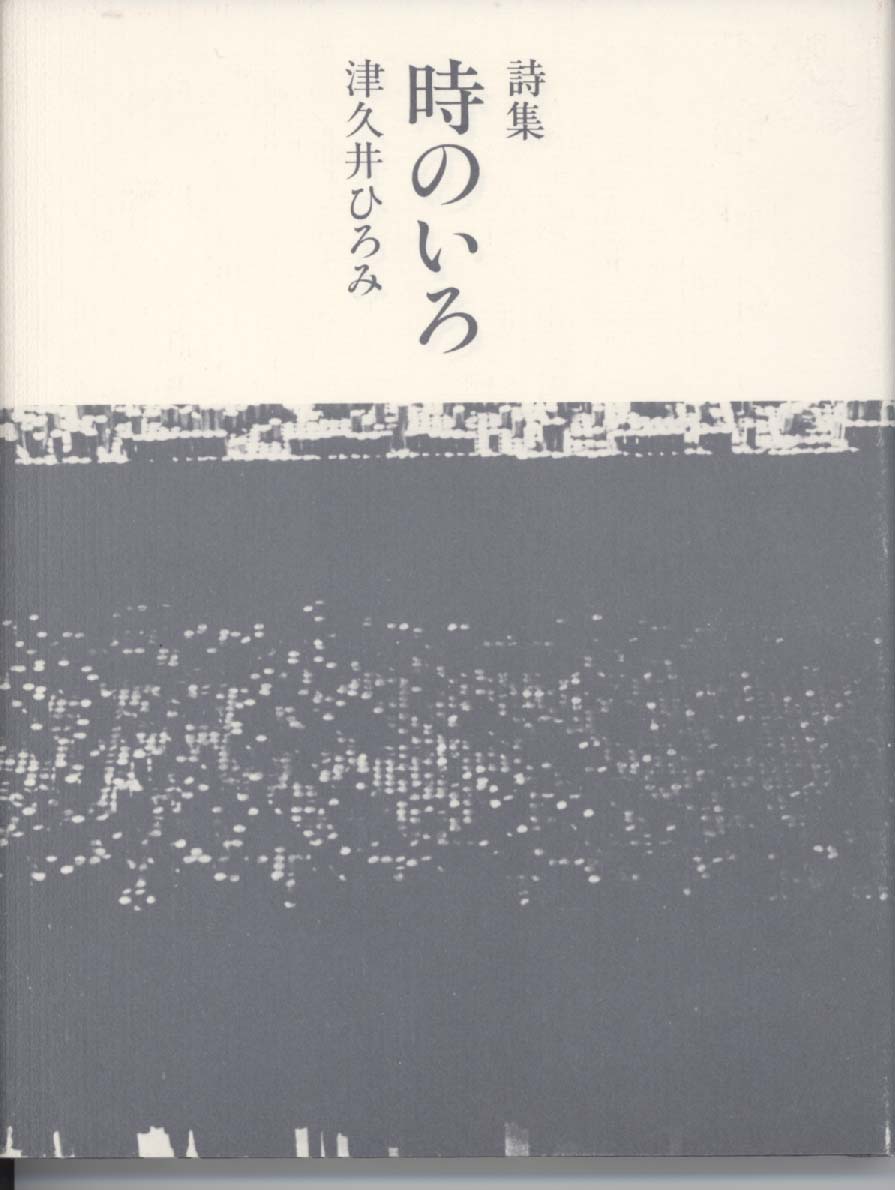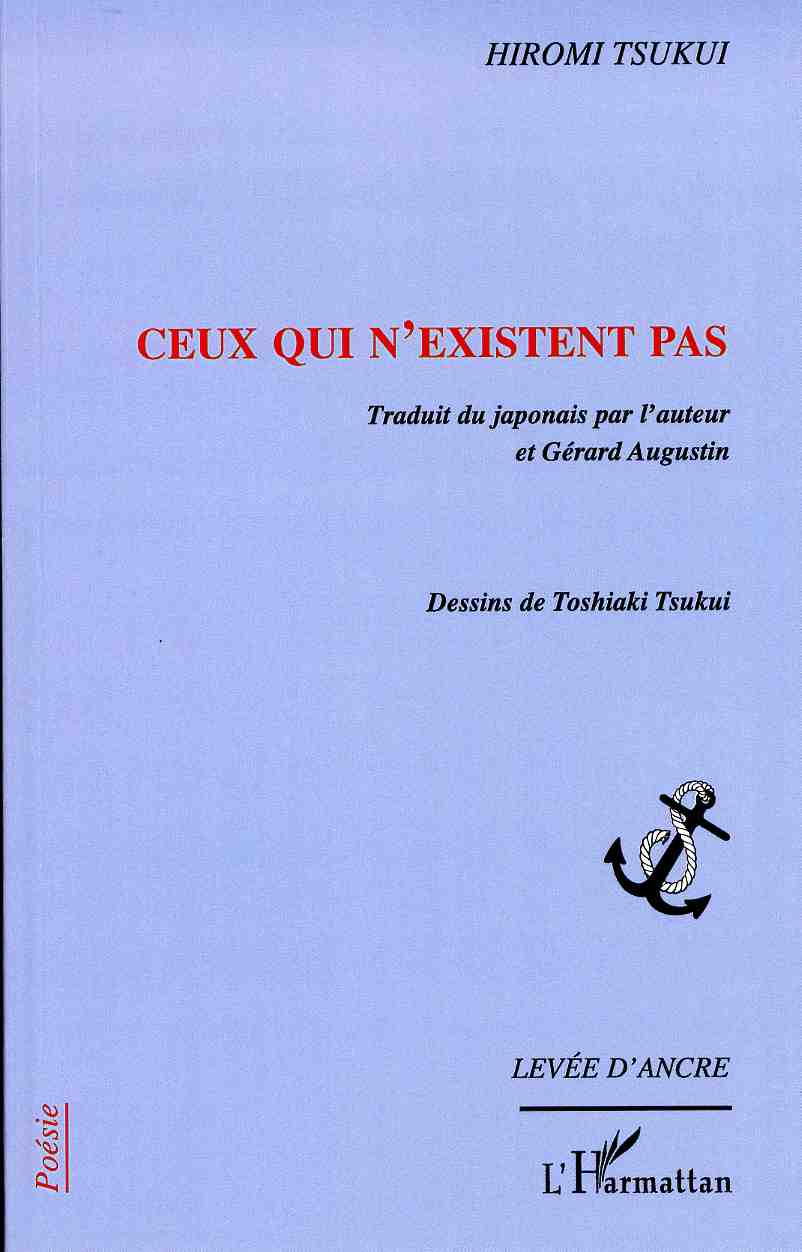
「彼女には独特な自然との関わり方があり、それは超微生物的なもの、忘れ去られたもの、隠れたもの、不可視のものたちと通じ合おうとする哲学に根ざしてい る。彼女はその対象物になりきろうとして歩き、あるいは水や風と云った基本要素のゆらぎにまで介入しながら、自然のもつ力へと密かに接近する。その姿勢を なぞらっていると、日本の神話や習慣、遠く未知のことばにまで既に愛着を抱くほど不思議な気持ちにさせられる。さまざまな風景や日本とフランスの入り混 じった生活様式が幾重にも焼付けられる詩句は、不思議さの境界を越えて、問題提起へと誘いこむ奇妙な能力を備えているのだ。」(ジェラール・オーギュスタ ン、紹介文より)

「宿しもつ月の光の雄々しさはいかにいへども広沢の池」
新幹線で京都に行き、タクシーでこの広沢の池の水際までたどり着いた。余りの池の小ささに可笑しくなってしまった。わたしが笑うと、水辺の波も笑いだし、 西行はあたまの中にある池の水ぎわから歩きに歩って、この風景を愛でたのに、オマエはタクシーで乗りつけて、水の干上がったあたまで笑うとは、、、西行の 波間 の水は、遥か彼方の水平線を越えて、裏がわのブルターニュの波間を、笑いのさざ波で、月の光を揺らしていると云うのに、、、
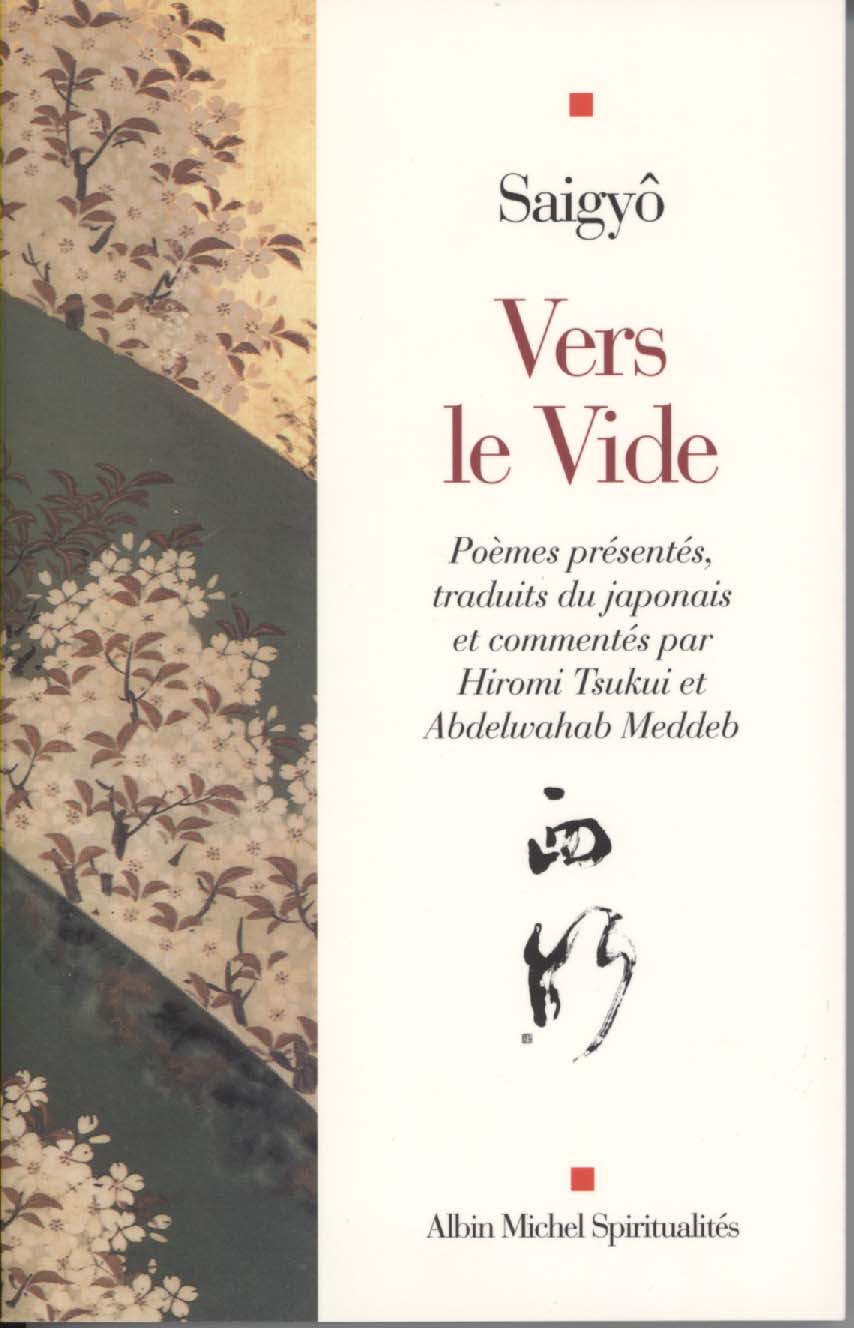
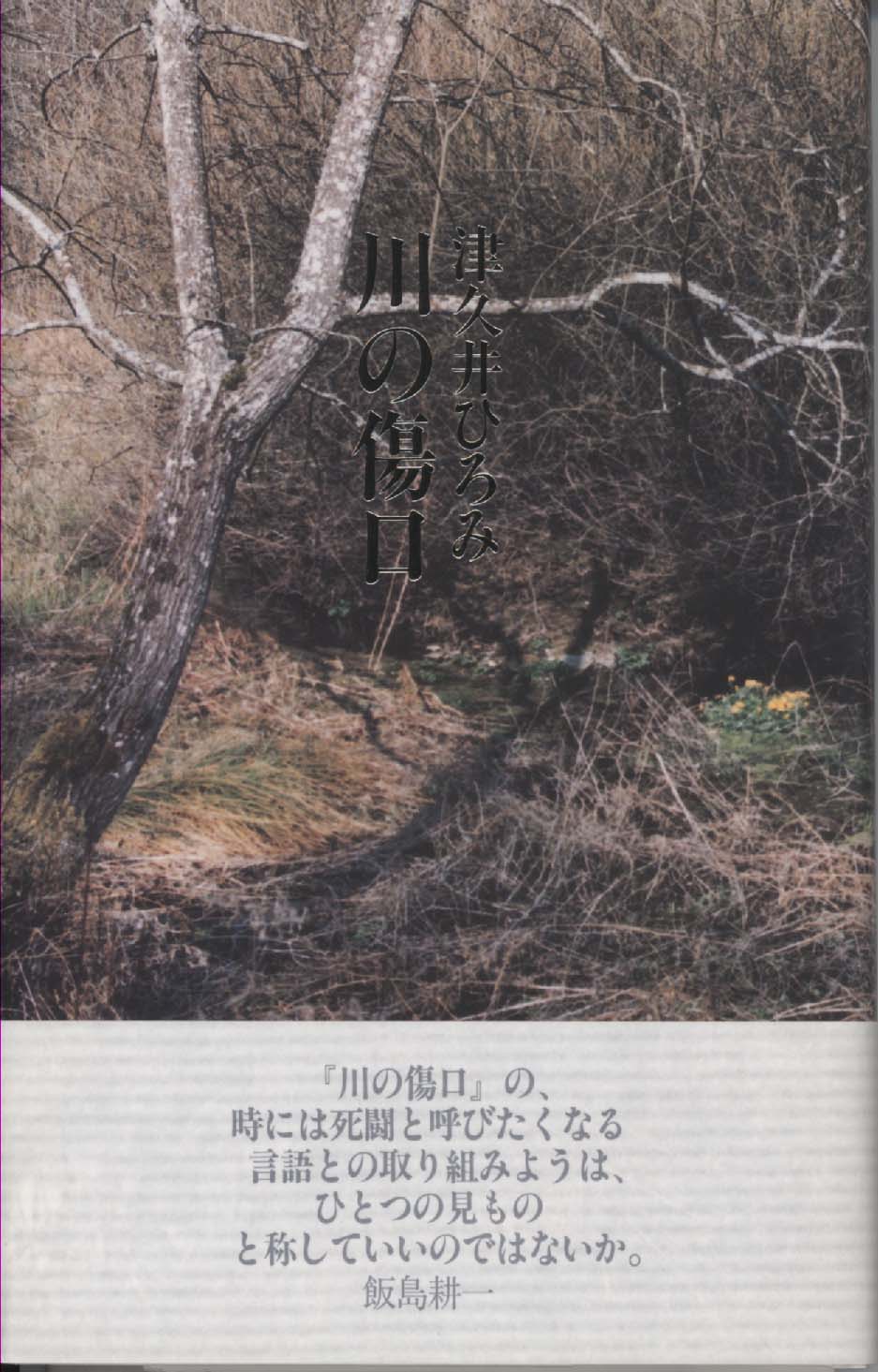
わたしの目の前の一杯の緑茶、この水分も、わたしの身体の水分も、辿ってゆくと同じ源泉だろうか。羊水には塩分が含まれていて、海水に近い歩みを見せる。 子宮の中で胎児は宇宙的な歴史の旅を短時間にたどると云う。生の波が宇宙のリズムに共鳴し合うとき、必ず何処かがひきつっているのではないか。
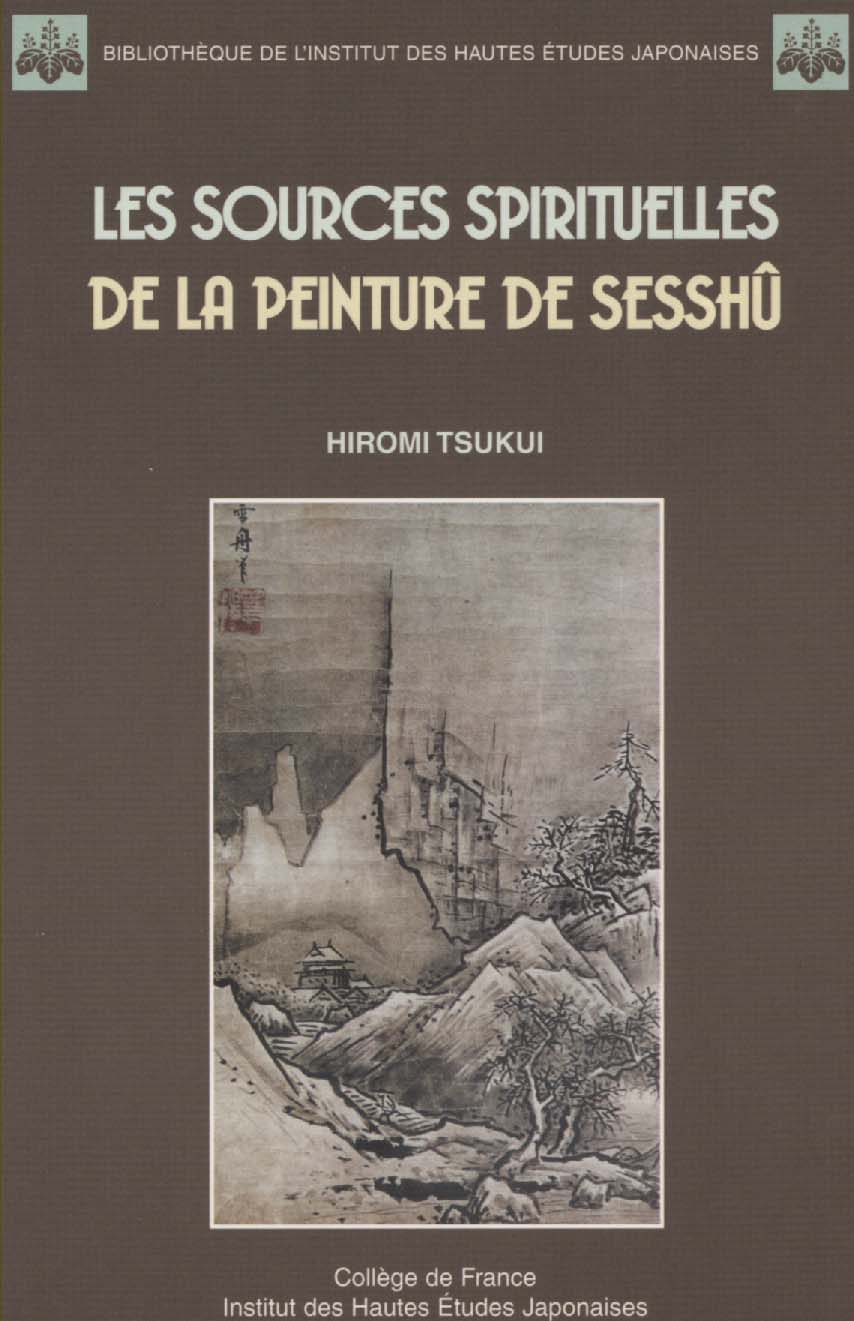
<雪舟画に於ける生命力が迸る独特な筆致の源は、一体何処から来るのだろうか? 山水画の道がどれほど宗教哲学的な精神のありようと無縁のものではないか、 そこを探ることに研究が集約されている。>エヴリンヌ・メニール(京都大学)は 「アジアの芸術(美術館年報)」の書評で、「中国の哲学(朱子の思想)は画家の生と 画業の内面化に豊かな展開の道をひらいた。絵によって宇宙の気韻を伝える境地に到るには、 先人の方法(手に得て、心に伝える)を習得し、さらにそれを乗り越える(心に得て、手に伝える)こと。 この歩み方は、あらゆる制約から解放される自在の精神へと鍛えられて行く禅僧のそれにも通じ、 著者が記すように、道元が示唆する“鳥飛沓々”(p130)なのであろう。」(54卷、1999)
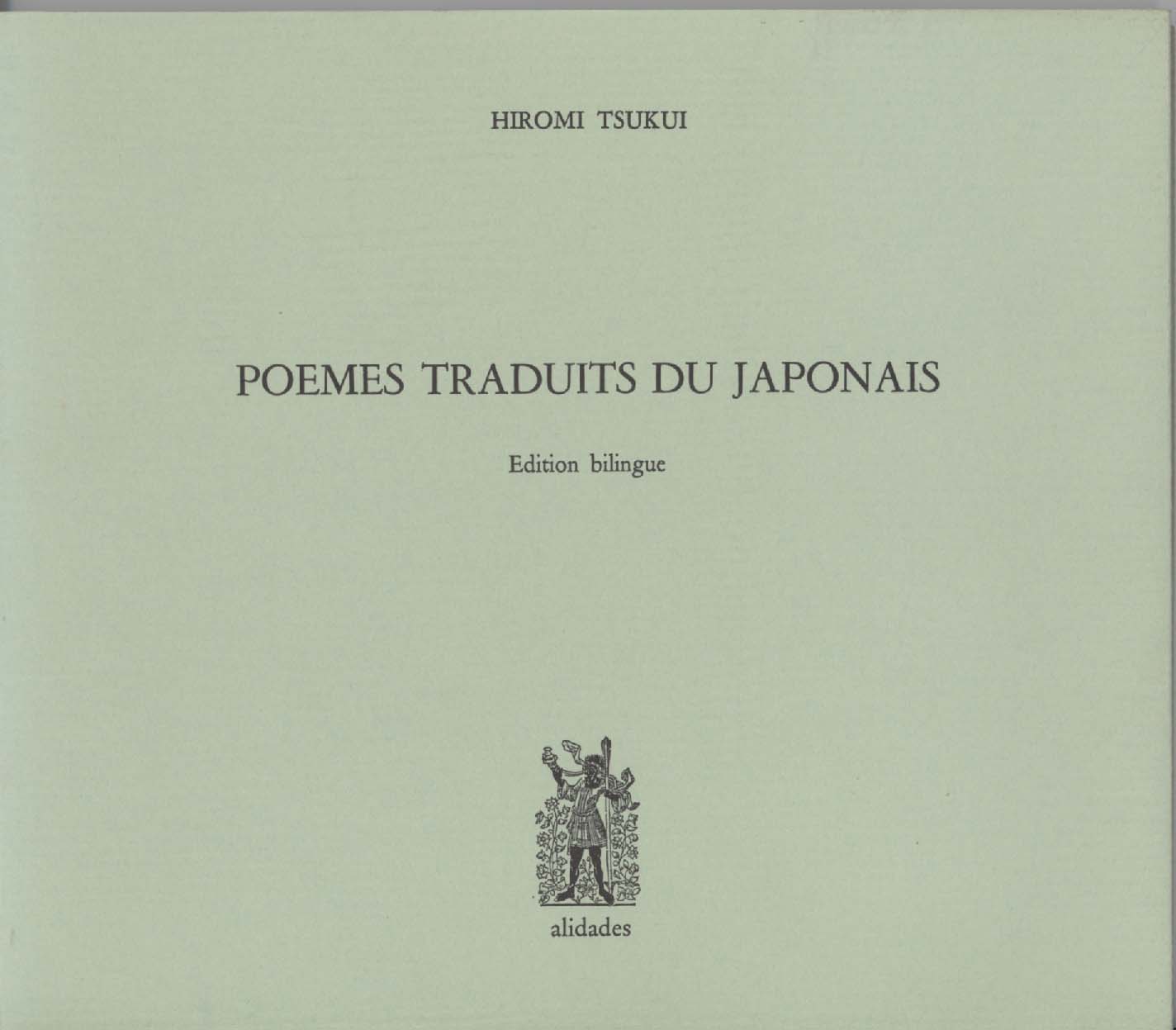
ベンタベリーはそのあとがきの中で述べている。 「さいしょに配慮される詩人の視線は、導くことではなく、 導かれること。その視線はもっとも微小なものに注がれる。 つつましいがしかし確かな決め手となる案内者たち、虫、あるいは鳥、 とりわけその影。影が顕れるつど、確かなものが約束されるのか、、、 […]“土を食べるもの“は影の中で生き蠢き、鳥は 自分の影の頂きへ向かって翔びながらその影を完成させる。彼らこそ、 彼らの生に沿って行く詩人の、詩作の場を正し、指し示す。」